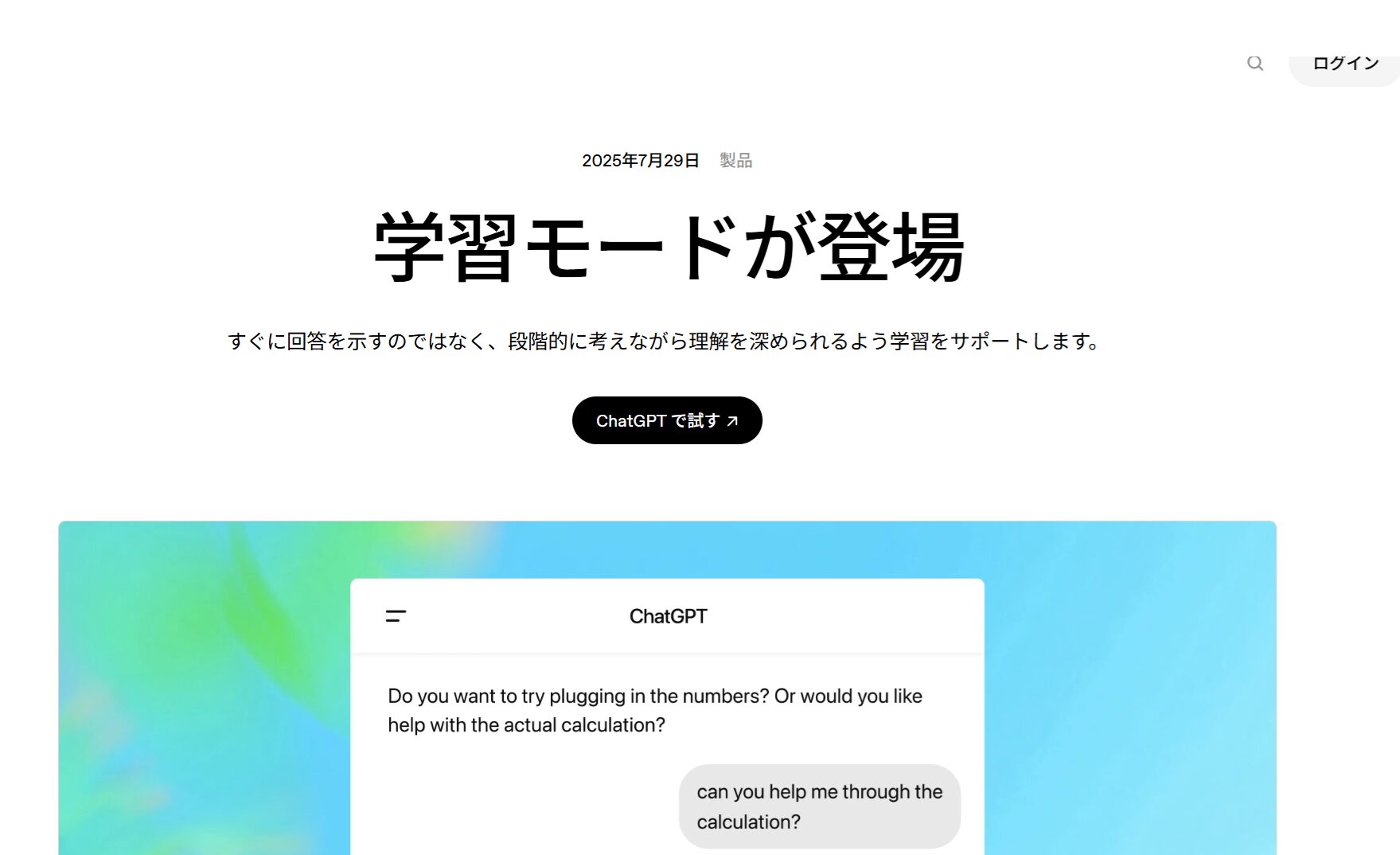OpenAIは7月29日、対話型AI「ChatGPT」に新機能「学習モード(英語名:study mode)」を実装したと発表した。宿題や試験対策で「答えを丸写しするだけ」と批判されがちだった生成AIを、能動的に考えさせる“デジタル家庭教師”へと位置付け直す狙いだ。
OpenAIは7月29日、「ChatGPT」に新機能「学習モード(Study Mode)」を正式導入した。従来は“答えを即座に表示するツール”と批判されることもあった生成AIを、解法を自分で導き出すための家庭教師的パートナーへ転換する狙いだ。
学習モードをオンにすると、ChatGPTが最初に学習目標や現在の理解度を問い掛け、その情報をもとにソクラテス式の質問、ヒント、ミニクイズなどを組み合わせながら段階的にゴールへ導く。回答は論点ごとに整理され、重要概念を分かりやすい単位で提示する設計になっている。
パーソナライズも特徴で、過去の対話や回答履歴を参照して難易度や説明粒度を自動調整する。途中で理解度チェックが入り、誤答した場合は追加のヒントや再説明が提示されるため、受け身にならずに学びを深められる。モードはワンクリックでオン/オフ可能で、通常のチャットとの切り替えは自由だ。
提供範囲は広く、リリース当日からFree、Plus、Pro、Teamの全ユーザーが利用でき、教育機関向けの「ChatGPT Edu」には数週間以内に展開予定とされる。iOS、Android、Web、デスクトップの各プラットフォームですでに動作し、どのモデルでも有効だ。
開発は40以上の教育現場の教員や学習科学者と連携して行われ、能動的学習やメタ認知といった研究知見をシステム指示レベルで組み込む手法を採用した。今後はユーザーのフィードバックを踏まえ、進捗トラッキングやビジュアル化、管理者によるロック機能などを追加しながらモデル本体へ統合していく計画だ。
教育分野は生成AI各社が注力する新たな主戦場で、同日にGoogleが「Gemini for Education」の拡充を発表するなど競争が激化している。OpenAIの学習モードは「深い理解を促すAI」というポジションを固め、若年層の利用を取り込む布石とみられる。
一方で、学生がモードを切れば従来どおり“答えだけ”を得る抜け道は残る。効果を確実にするには学習者自身の動機づけと、教育現場での活用ルール整備が不可欠だ。OpenAIが掲げる今後の改良が、導入のハードルと実際の学習成果をどこまで両立できるかが注目される。